上田吉一 詰パラ1969.5
手数は中編にはいるが、内容は短編。
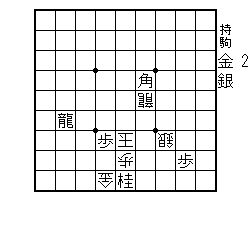
初形を眺めているとある収束が見えてくる。
48に逃げ道がある。これを防いで66角だと86龍の利きを角が塞ぐので46玉と逃げられる。
そこで先に46龍と捨てる筋だ。同龍に66角。
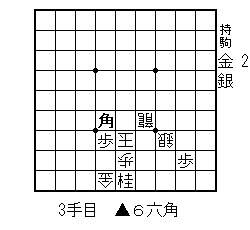
同龍に47金までという5手収束。
しかし本図には2つの問題がある。
一つは68に逃げられること。どこかで68☗、同金の2手が入るはずだ。
もう一つは56玉と逃げられること。66角ではなく66馬でなければいけない。角を馬にする順が事前に必要だ。
ではどちらから着手するべきか。
強力な馬を作っておくのが常識的な線だろう。
持駒を消費してから馬を作るのが正解という作品ができたらそれは常識をひっくり返す傑作だ。
その線でまずは角を動かす。
66角、68玉、
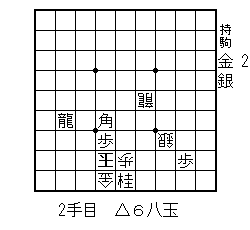
さて最初の問題は66角に46玉ならば33角成と馬が作れそうだが、それは玉方も承知なので68玉と潜られたらどうするかということだ。
それなら先に68を埋めてしまえと進めると……
77角、57玉、68銀、同金、66角、46玉、
33角成、56香、
【失敗図】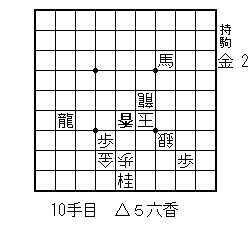
やはり持駒を減らしてから33角成では56に間駒されて……駒が足りない。
ということは作意は66角、46玉のはず。66角、68玉は変化でなければいけない。
この変化に好手が登場する。
(66角、68玉に)79金、
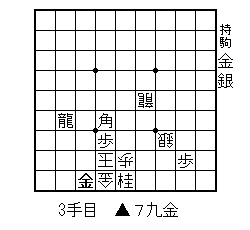
79金がこの一手の好手だ。
同玉は88龍まで。
同金は77龍、59玉、68銀、49玉、39金まで。
59玉は69金、同玉、89龍、79金、78銀、68玉、69金、同金、同龍まで
これで無事に2手目は46玉と確定した。
(66角、)46玉、
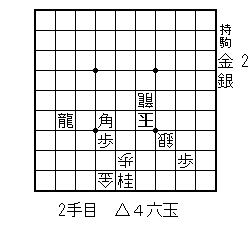
待望の33角成だが、間駒の変化を潰しておこう。
33角成、56香、47金、35玉、36銀、同龍、
同金、同玉、56龍、46金、27金、35玉、
34飛、25玉、24馬まで
【変化図】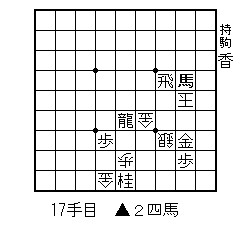
これでまずは角を馬にすることができた。
33角成、57玉、
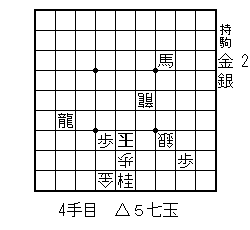
この局面で66馬、46玉、33(44)馬、57玉を好きなだけ繰り返せるのが本作唯一の弱点だ。
さて、もう一つ解決すべき問題が残っている。
持駒に金を1枚残す必要がある。そこで68を埋めるために使える手駒は金銀だ。
次の二択が最後の問題だ。
- 68金、同玉、77馬、57玉、68銀、同金、
- 68銀、同玉、77馬、57玉、68金、同金、
要は金銀どちらを先に使うのが正解かということだ。
これもちょっと落ち着いて考えると68銀ならば59にも利きがあるので48玉と逃げられたときに効果的だ。
それなら持駒が寂しくなってくる後に使うのが正解だろう。
確認するためにあえて先に銀を使うと……
68銀、同玉、77馬、57玉、68金、48玉、
66馬、59玉、69金、同玉、89龍、79金、
【失敗図】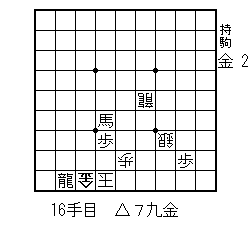
最後の間駒は銀でも詰まない。
さてこれで大駒2枚を捨てる爽やかな収束を味わうだけだ。
68金、同玉、77馬、57玉、68銀、
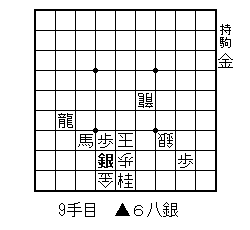
68金に48玉は66馬、59玉、69金、同玉、89龍、79金、68銀以下。
同金、66馬、46玉、44馬、57玉、
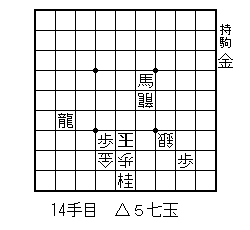
これで準備はすべて整った。
46龍、同龍、66馬、同龍、47金まで19手詰
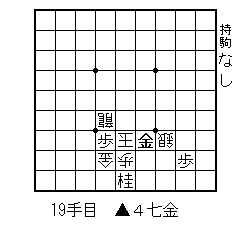
この収束から逆算して創作したと仮定してみよう。
最後の5手詰で不要な駒は28歩と37銀。
これを44馬以下の7手詰にする際に37銀が必要になる。
さらに4手逆算して68銀以下の11手詰にする際に28歩が必要になる。
そしてそこから19手詰になるまで盤面の駒数は変化していない。
余詰防ぎの意味しかない駒など皆無である。

角を持駒にせずに44角と配したところに作者の詰棋観が窺えます。