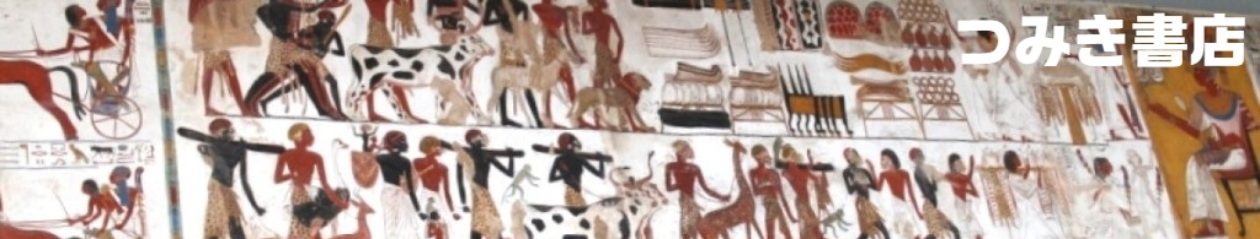柳原裕司さんから、メールをいただいた。
第2代詰将棋パラダイス編集長。
知らなかったという方は覚えておこうw
玉手箱、いつも楽しみに見ています。
ちょっぴり、鶴田時代の誌面を思い出させて
くれるところが好きです。最近「饗宴世代」の方々がとても元気で
嬉しく思っています。長い冬眠生活の私ですが、
「この詰2009」の予告を見て
思わず飛び起きたひとりです。
これは・・・すごい。
マニアの私にはあまりにも刺激が強すぎます。発刊まで、これほど待ち遠しいと
思ったのは現役以来です。
こういうのをずっと待ってました。
小泉さんの論考も楽しみです。
おお、「この詰」の企画がベールを脱いだのですね。
これで堂々と(?)「この詰」について書いてもいいんだ。
(今までもtwitterではつぶやいていますけど(^^))
『この詰将棋がすごい! 2009年度版』予告
Paradise Booksの1冊として、『この詰将棋がすごい! 2009年度版』の編集が進んでいます。ここでその内容を公開しておきます。本体130ページほどで、販売価格2000円の予定。発行は6月。
以下、カッコ内は執筆者を表します。第1部 2009年度ベスト詰将棋
*短篇ベスト12局(原亜津夫)
*中篇ベスト8局(安江久男)
*長篇ベスト4局(伊藤正)
*フェアリーベスト8局(山田嘉則)第2部 オールタイムベスト詰将棋
特集1 巨椋鴻之介
*巨椋鴻之介インタビュー(聞き手:小林敏樹、角建逸、橋本哲、若島正)
*巨椋鴻之介の好きな8局
*巨椋鴻之介ベスト8局(橋本哲)特集2 森田拓也
*森田拓也インタビュー(聞き手:伊藤正、若島正)
*森田拓也の好きな4局
*よみがえる「北斗」と「長城」…修正図2作企画1 ライバルを語る
*高坂研のベスト4局(市島啓樹)
*市島啓樹のベスト4局(高坂研)企画2 解答者登場
*秋元節三の好きな4局(秋元節三)企画3 テーマ評論
*超短篇における中合対策の研究(小泉潔)企画4 作家を再評価する
*小川宏ベスト8局(小林敏樹)
*OT松田ベスト4局(伊藤正)
*高木秀次ベスト8局(若島正)第3部 創刊記念スタッフ座談会
*出席者:小泉潔、高坂研、小林敏樹、角建逸、橋本哲、原亜津夫、山田嘉則、若島正
柳原さんが飛び起きたのもむべなるかなというべし。
若島さんが昨年の全国大会で高坂さんや小林さんに配っていた企画案をのぞき見した途端、絶対に読みたくなった。
そしていままでずっと読みたい。
実は小林さんの推薦でオイラの原稿も拾ってもらったので、ゲラを読むことは可能なのだが、我慢できなかったいくつかを除いてあえて読まないで我慢している。(正式スタッフでないから、校正する義務はない。たぶん)
ちゃんと本になってから一気に読むんだ。
きっと発売は全国大会だろう。
今年は東京。楽しみだ。
Tweet