昨日の門脇さんの「手順の解説が少ない」で思い出した話をもう一つ。
詰将棋入門(212)で小西逸生の「46角」という作品を紹介した。
小西逸生『紅玉』第55番 近将1958.9
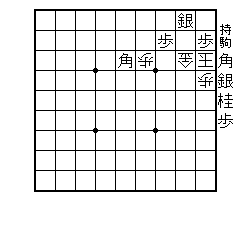
46角、22玉、11銀、21玉、31角成、12玉、13角成、11玉、
22馬左、同金、23桂、同金、12歩、21玉、31歩成まで
15手詰
この作品についての『紅玉』に収められている解説が面白かったので紹介する。
そんなに長くないので全文引用してしまおう。
続きを読む 『紅玉』の解説から
昨日の門脇さんの「手順の解説が少ない」で思い出した話をもう一つ。
詰将棋入門(212)で小西逸生の「46角」という作品を紹介した。
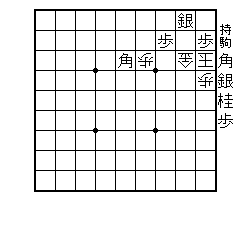
46角、22玉、11銀、21玉、31角成、12玉、13角成、11玉、
22馬左、同金、23桂、同金、12歩、21玉、31歩成まで
15手詰
この作品についての『紅玉』に収められている解説が面白かったので紹介する。
そんなに長くないので全文引用してしまおう。
続きを読む 『紅玉』の解説から
田宮さんが亡くなられたそうだ。
ご冥福を祈ります。
私にとって田宮さんはまず「ヤン詰の担当者」だった。
今はヤン詰は「中級」となっているが、田宮さんの作ったヤン詰は創作初心者にターゲットを絞った物だった。
投稿すると詳しく余詰指摘されて返ってくる。
履歴が分かるように、その返送された投稿用紙の上に修正図を貼り付けるというルールだった記憶がある。
今の新人コンクールは非常にレベルが高くて、どこが新人なんだと恐れ入るばかりだが、
当時のヤン詰は私を含め、ホンモノの初心者が遊べる場所だった。
ヤン詰出身を自認している作家は結構居るのではないかな。
解答を送ると、「どたまのトレーニング資料」というリコピー版の冊子を貰えた。
手元に残っているのは次の通り。
柳田さんも書いていたが、川崎さんとの規約論争も生き甲斐だったようだ。
「詰棋討論」はコピー誌で30cmぐらいは読んだが、今は処分してしまって残っていない。
「将棋パズル」もほとんど残っていない。
服部さんなら全部持っているのかなぁ。
三鷹から我孫子に移られてからは、あまりお会いする事も少なくなった。
でも、一度我孫子に遊びに行ったら、やはり子どもたちを集めてパズルやゲームで楽しく遊んでいた。
私も引退したら、近所の子どもたちを集めて怪しい遊びを教え込んで暮らそうかなぁ。
昔、7手詰作品集をまとめることを考えていて、ほぼ出来上がったので、田宮さんに序文を依頼した。
そして序文を頂いておきながら、作品を眺めているうちに、9手詰の頭2手をカットした7手詰や、5手詰で出来ているのにつまらない2手を逆算した7手詰などが目について、いやになって止めてしまった。
完成した小冊子を田宮さんに贈れなかった事が心残りだ。
Tweet