若島正『恋唄』第22番 詰パラ1972.3
入玉形だがスッキリした形。ここから間駒の妙技が出現する。
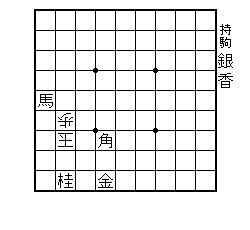
銀香の持駒ではなかなか攻めづらい。香を活かす攻めは……
96馬、同玉、99香、
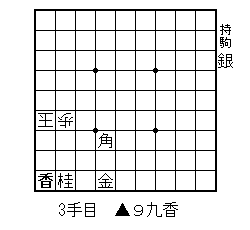
67角が85をちゃんと抑えている。
87玉なら78金まで!
ということは98へ中合する必要があるのだが、その駒は
98飛、
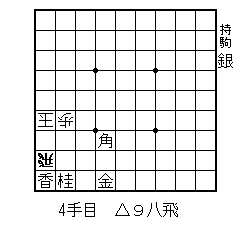
飛車の中合。以下仮に進めると……
同香、87玉、77飛、88玉、79金、99玉、
88銀、98玉、97飛まで
【変化図】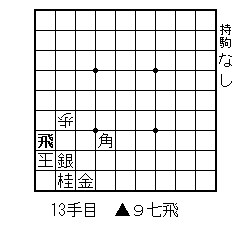
無論、このベタベタした手順は変化だ。
では、どう応じるのが正解か。
(98)同香、97桂、
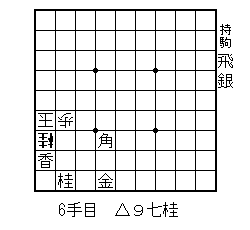
98飛の只捨てで98への逃走路を確保した上に、更に97桂と捨合する。
その意味は……
同香、87玉、77飛、98玉、
【失敗図】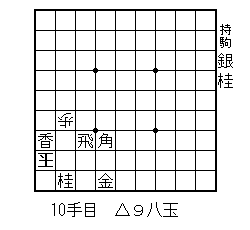
先程の順では98玉と香を取ってしまったが、97桂と捨てることで97香の形で盤上に残す。
結果、【失敗図】のように攻方は97飛ができなくなり不詰となるのだ。
ということは、77飛の攻めを断念する必要がある。
(97)同香、87玉、78金、98玉、
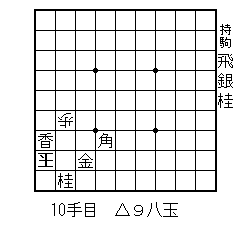
97の間駒が頭に利く駒、例えば歩だったら、ここから99歩、同玉、88銀で詰む。(角なら78金の所で76角打)
しかし桂馬では入玉されて一体何処で使えるのか。
発表時の解説によるとここまで進めて「不詰」と判断した解答者もいたそうだ。
実際、もう粘性の駒はないし……
88金、同玉、78飛、
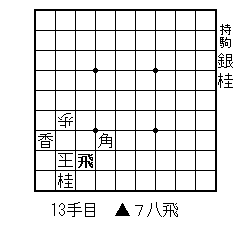
金をあっさり捨てて飛車に打ち換えるのが後続手段。
開き王手で龍を作る狙いだ。
99玉、88銀、89玉、77飛成、
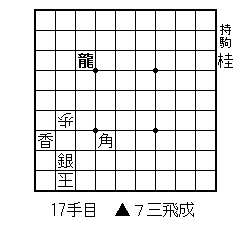
龍はできた。
が、銀も投資してしまい持駒は残り桂馬1枚だが
88玉、78龍、97玉、89桂、96玉、
98龍まで23手詰
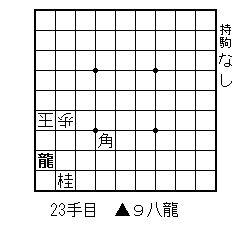
間駒で得た飛桂がきっちりと玉を捕らえている。
作意手順を進めるのを急いだが、変化にも小粋な手が現れる。
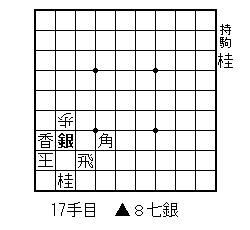
上は88銀に98玉と逃げたときの87銀だ。
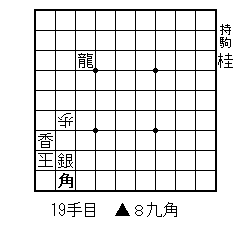
これは73飛成に98玉と逃げたときの89角!
この作品が『恋唄』には収録されているのに『盤上のファンタジア』には収録されなかった理由はおそらく次の変化が理由だ。
78飛に堂々と89玉とした変化。
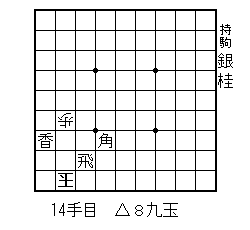
以下、73飛成、98玉、78龍、88角、89銀、97玉、88龍、96玉、63角、95玉、85角成まで25手駒余り
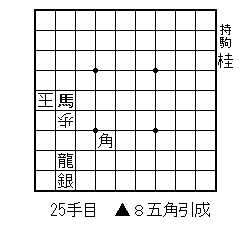
変長(変化長手数駒余)だ。
発表当時は変長はルールで問題なし(ただし評価は下がる)とされていた。
そしてこの作品は変長があるにもかかわらず、解答者の圧倒的支持を集めている。
いつのまにか誰によってか分からないが「変長は不完全作」とルールが変えられたという詰将棋界の歴史がある。
しかし、問題なく出題されていた作品が、後になって闇に葬られてしまうというのは変な話だ。
かといってアンソロジーを編む際にいちいち「当時は変長が認められていた」と注釈をつけるのも面倒だし、「現在は不完全扱いなのか」と受けとられると考えると、そもそも選ばれなくなる。結果的に闇に葬られるという現実がある。
なお99香、98飛の手順は先行作がある。
秋元龍司 詰パラ1971.9
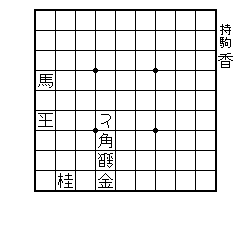
これも必要だった94馬が邪魔駒と化す見事な作品。
13手詰なので初見の方のために作意は書かないでおこう。
なお若島氏はこの作をヒントにしたわけではなく、「秋元作の発表前に投稿されている」という担当者の言葉がある。偶然の一致だ。
Tweet