伊藤看寿 『将棋図巧』第39番 1755.3
64-28のラインに並んでいる玉方の歩がすべて消えて無くなる。
易しい趣向作。
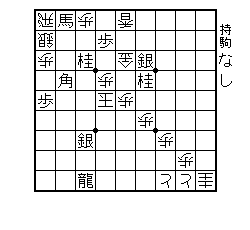
導入はいきなり銀での追い趣向。
66銀、56玉、57銀、47玉、48銀、38玉、39銀、
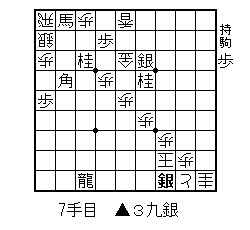
ここで銀と龍がバトンタッチ。
今度は龍で追い戻していく。
同と、同龍、47玉、48龍、56玉、57龍、65玉、66龍、74玉、75龍、
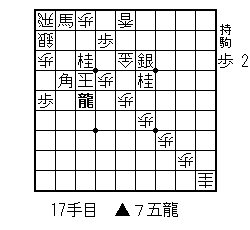
軽い斜め一往復の趣向。
この舞台を作っていた81馬と64-19ラインの並んだ歩。
これらが消えていくのがメインの趣向だ。
83玉、82馬、同玉、81桂成、
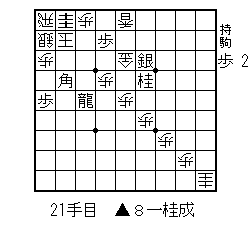
凝り形をほぐして、最初の角不成が登場する。
同玉、82歩、同玉、73角不成、
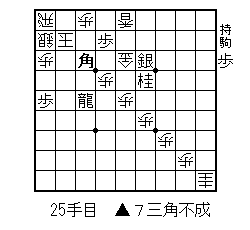
もちろん成れば81玉で打歩詰。
72玉では91角成と飛車を抜かれるので、玉方としては82歩を打たせて飛車を守る。
81玉、82歩、72玉、64角不成、
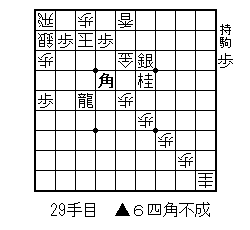
開き王手でも角不成。
62玉、73角不成、61玉、62歩、72玉、55角不成、
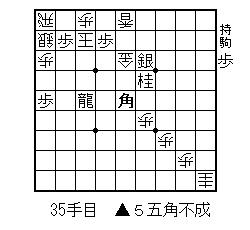
やはり51香を守るため、62歩を打たせるのが玉方の対応になる。
この6手のユニットが繰り返される。
6拍子5小節の角による並び歩の連取趣向。
62玉、
73角不成、61玉、62歩、72玉、46角不成、62玉、
73角不成、61玉、62歩、72玉、37角不成、62玉、
73角不成、61玉、62歩、72玉、28角不成、62玉、
73角不成、61玉、62歩、72玉、19角成、
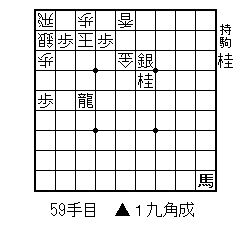
目的は19の桂馬を入手すること。
62玉、73馬、61玉、64龍、
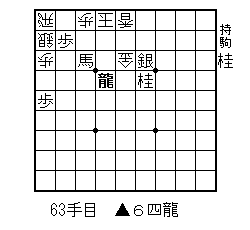
大塚播州氏は質駒を獲る駒を主駒、その際王手をする駒を親駒と命名している。
氏の用語を用いれば、親駒である龍を鮮やかに捨てて短く収束する。
同金、53桂、同香、52銀成まで67手詰
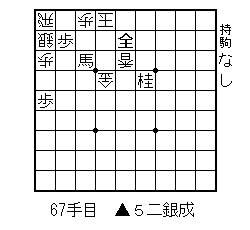
序に斜め一往復を入れる辺りの技術は流石だが、全体的に「難しくしよう」という意識は皆無のアイデアだけで勝負というタイプの作品だ。角不成11回も狙いなのだろうか。
「面白い手順を繰り返す」ことは幸せだ。
といっても千日手になっては詰将棋にならない。
この作品は並んだ駒をスイープすることにタイマーの役割を持たせている。
楽しい夢を見ているのは歩がまだある間。
桂馬が獲れたら目覚ましが鳴るという仕組みだ。
この連取り趣向は多くの作家が様々な工夫をつけくわえ数多くの作品が発表された。
なお本図には35手目55角不成、62玉の後、73龍以下の余詰がある。
門脇芳雄『詰むや詰まざるや』には玉方21桂配置という加藤文卓氏の補正案が紹介されている。

この図に玉方21桂は似合わない。
もしも看寿が余詰に気づいても、絶対にこの修正案は採りそうにありません(^^)
私も同じ気持ちだったので図面も用意しなかったのですが……考えてみると難しいですね。
私も修正案を考えてみました。
53金⇒53成銀
……いかがでしょう。
収束54龍に香合は53金でも変長なので、そこも生かした(?)修正案です(^^)