志駒屋十政 詰パラ1988.08
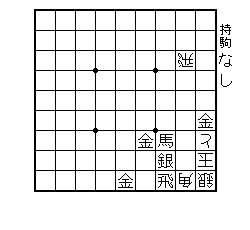
第16問について護堂さんが触れていた山腰作ってこれでしょうか。動く将棋盤は末尾においておきます。
さて残りは長いのが2局! でも頑張って終わらせます。
続きを読む 詰将棋つくってみた(197)
課題39:結果発表(6)
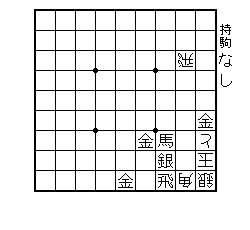
第16問について護堂さんが触れていた山腰作ってこれでしょうか。動く将棋盤は末尾においておきます。
さて残りは長いのが2局! でも頑張って終わらせます。
続きを読む 詰将棋つくってみた(197)
課題39:結果発表(6)
このペースで結果発表すすめていったら、もしかすると3月中に終わらないかもしれませんね。
4月1日には第7回三手詰祭が待っているというのに…。
それはともかく、みなさま三手詰の投稿お待ちしています。
続きを読む 詰将棋つくってみた(193)
課題39:結果発表(4)
昨日の第4問の参考図を紹介するのを忘れたので、桜井作の鑑賞からはじめよう。
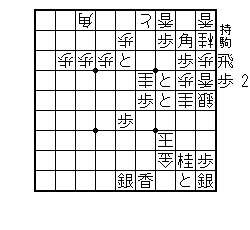
★過去作を知っている人と知らない人で、新作の評価が変わってくるのは当然のこと。第4問に対するJudgeの講評を読んで「厳しい」と感じた方も、本作を知った上でもう一度読み返してみるとまた違った感想になるかもしれない。
続きを読む 詰将棋つくってみた(191)
課題39:結果発表(2)
総手数1000手を超える解答募集というキャッチコピーがいけなかったのか、解答者は11名でした。
感謝です。
そして投稿作を増やすためには、解答者の増加が鍵です。
よろしくお願いいたします!
続きを読む 詰将棋つくってみた(190)
課題39:結果発表(1)
Judge:護堂浩之
<はじめに>
「私がジャッジすると、昭和の評価軸に基づいたものになりますよ」と、風氏に念を押したところ、それで構わないとのことだったので、老頭児が鑑賞・判定することになった。過去データの蓄積はあるが、現代風のカテゴライズは出来ていない人間の偏見であることをお断わりしておきたい。
従って、ここで批判を受けたとしても、昭和の人には分かってもらえなかったんだね――と思っていただければ、良いのではないか。
課題39への投稿ありがとうございました。
課題39 馬鋸を含む詰将棋を作ってください。
たまには長篇もよいだろうと設定した課題です。
馬鋸は数多くの作品がすでに発表されているので、作ってはみたものの新作として発表するにはちと荷が重い……そういった在庫を一掃して貰おうという意図もありました。
その意図は当たってか……22作もの作品が集まりました。合計の手数は1600手を超えています(^^;;
しかし、馬鋸部分は1サイクルを解明すればあとは繰り返しなので、手数ほど難しくないのも嘘ではありません。(第7番がオススメです。昔タイムトライアルに出題していた作品)
悩んだ結果、少しだけ締切を延ばしました。
印刷用pdfつくりました⇒課題39.pdf
a4両面印刷で持ち運びしやすいサイズになります。
続きを読む 詰将棋つくってみた(187)
課題39:解答募集
課題31への投稿ありがとうございました。
今回の課題は「持駒趣向」でした。
何人もの方から大量投稿をいただいて、今回はかなりボリューミーになりました。
どうぞ数多くの解答をお願い申し上げます。
印刷用pdfつくりました⇒課題31.pdf
a4両面印刷で持ち運びしやすいサイズになります。
続きを読む 詰将棋つくってみた(144) 課題31:解答募集
Tweet2010.1から3年半続けた詰パラ大学院での解説の再録です。
在庫の中で最も多いのが馬鋸作品だ。
馬鋸は仕掛けが比較的簡単でバリエーションも多いということがその理由だろう。アレンジしやすいのだ。
解答者の人気も高い。無駄合について甘く理解されるのも、馬の雄大な動きが人気だからと理解している。
しかし馬鋸作品もすでに数が非常に多い。誰もがこれは新鮮だと目を見張る作品を創るのは厳しくなってきた。
今月はそんな閉塞的な状況を打開すべく期待の若手二人が立ち上がる。新鮮味を求めるアプローチの方向がまったく違う所が見物だ。
いずれも作者の工夫が解れば収束は平易であるので、多数の解答を期待しています。